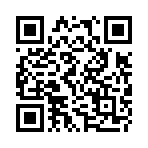2020年06月10日
Posted by {^L^} at
2020年06月10日08:00 Comment(0)
冷やしカレー@清水屋

冷やしカレー@清水屋
今日も暑かったですねぇ~。 明日からは雨マークが続いてちょっと涼しくなりそうです。
暑いときには熱いカレーが欲しくなるものですが、うどんだと冷たいカレーが良いですよね。
香川の冷やしカレーと言えば、清水屋さんが先駆者です。なんと言ってもビジュアルが素晴
らしいです。




今年も冷やしカレーが始まったと聞いて、行って来ました。清水屋さんも色々コロナ対策
してますね。大きな点でいうと、天ぷらの前のビニールですが、清水屋さんの場合は天ぷら
置き場の前で、もう注文もうどんも受け取ってますから、天ぷら置き場では声を出しません。






まあ、○○を揚げて欲しいという場合は声をだすかも知れませんが、普通は黙って取るだけ
なので、ここはあえてビニールは要らないと思うんですけどね。。
変にビニールで覆うと天ぷらを取るときに手でめくらないといけないので、余計接触機会が
増えるような気がします。

そして、レジの前のネギ置き場に薬味が置かれなくなってます。大根下ろしとか、レモンは
カウンターでうどんを受け取る場所に置かれてます。
大きな変更点はこの2ヶ所ですかね。七味は各テーブルに置かれてます。
おでんが、うどんを注文をする場所に置かれているのと、天ぷらのビニールが下まで覆い
過ぎなのが、気になる点です。



さて、冷やしカレーのビジュアルにはいつも惚れ惚れしますねっ! 野菜たっぷりが謳い
文句ですが、食物繊維摂取を意識してか、レンコンも分厚く切られてます。

なんと言っても、清水屋さんの冷やしカレーの醍醐味は、これでもかというぐらいの剛麺に
冷たいカレーが良く絡むことです。物理的にトロミが付けられているので、もう粘着なカレー
なんです。
どんぶりに口を付けてカレーを飲もうにも、カレーが来ませんね。汗
ちょっと酸味が有っても良いと思うですが、梅干しだと思った赤いのが、ミニトマトだった
のには残念。涙
カレーのとろみのおかげで、一滴もカレーを飛ばさずに、食べ終わることが出来ました。\(^^)/
コロナのお時間です。
さて、今日はアフターコロナのうどん屋のあり方を考えてみます。
とにかく、行列店はお客さんが押し寄せると近所の人から嫌がられますが、普通のお店は
もう、集客しても駐車場からクルマが溢れたり、路上に行列が伸びなければ、嫌がられる
事は無くなったと考えられます。
特に香川のように感染が0で押さえられている場合は、この後高温多湿の7月、8月に
なるとコロナの話題も減り地元の神経質な対応は収まって来ると思われます。
しかし秋以降、次の感染者第一号が、うどん屋から発生ということを防ぐためには、お店の
仕組みを感染対策重視にする必要があります。
香川のうどんは、オーバーツーリズムな所がありましたから、アフターコロナは持続可能な
サステイナブル・ツーリズムに変える必要があります。
山越さんや、香の香などの人気店は、オーバーツーリズムが限界に達していたので、ここで
一旦仕切り直しする良い機会と思います。
一般観光地になぞらえて考えると、行列店の混み具合をオンタイムで発信することが考え
られます。一番簡単なのは、行列をライブカメラで配信することですが、県立公園でもない
個人のお店が単独でやるには、金銭的ではなくノウハウ的なハードルがあります。
本格的なライブ配信システムを構築しても10万円そこそこも有れば、ハードは揃い、後は
Wifi代だけですから、行列店の警備員の費用から考えると1日分の経費です。
うどん屋さんには技術的なノウハウが無いので、この辺りはなんらかの行政の支援が
必要なところです。
むやみに給付金を出すだけでなく、費用対効果の良い具体的なソリューションにも補助を
奨めるべきです。
お客さんが一極集中しないように、うどん屋巡りを県内の隅々まで広げることも重要でしょう。
大体目的のうどん屋を地図に落とし込んでうどん屋巡りをする訳ですから、目的のお店が
県内の各所に分散すれば、自然と一極集中が抑えられます。
コロナ収束後は行政によるスタンプラリーなんかが始まると思いますが、前回評判の良かっ
た「うどんコレクションスタンプラリー」のように、うどん屋さん側からの提案型の企画も
同時進行すると効果的と思います。
旅行業界には、安倍総理が 【 強盗キャンペーン 】と言い間違えて知られることになった
Go To トラベルキャンペーンのように1兆6千億円もの補助金がばらまかれる訳ですから、
対象にならないと思われる 【 うどん業界 】 には、県なり、市なりの補助金が必要で
しょう。
持続化給付金に使う予算の一部をうどんツーリズムにも是非適用して欲しいですねっ!
うどん屋さん側にも今一度、コロナ対策を見直してもらう必要もあると思います。
何度も書いているように、GWの時には準備不足と、なにより対策が手探りだったので
効果的な対策が出来て無いのが実情です。
うどん屋の大将も、お休みの日は他店を回って、他所のお店がどんな対策をしているか
良いところは学んで、あれ無用だなと思ったら自分のお店も無用な部分がないか置き換え
てみることも必要でしょう。
とにかくお客さんは、お店のコロナというか衛生管理の姿勢を見ています。
ここをおろそかにすると、自分のお店だけではなく、うどん業界全体の足を引っ張って
しまうので、力を入れて欲しい部分です。
天ぷらの注文部分の飛沫の問題と、トング等使い回しの道具を対策する必要が有ります。
このついでに、さぬきうどん界で評判の悪い、食べ残しをバケツに捨てるシステムとか
何年も使って手垢で真っ黒な七味の瓶なんかはこの機会に改める必要があると思います。
東洋経済オンラインに掲載された旅行業界の変革の記事を紹介しておきます。
https://toyokeizai.net/articles/-/354108
海外への旅行の部分をうどんを食べに海を渡ると読み替えてください。
------------------------------------------------------------------------------
「コロナ後の旅行」は"3つの点"で大きく変わる
①旅に求める意義が変わる
感染リスクが今後も続く中では、世界の旅人たちにとっては「長い時間をかけて移動して
まで日本に行く、その旅の意味は何か?」が重要になります。
世界的な旅行メディアであるCondé Nast Travellerの英国版でライターのJuliet Kinsman氏も
「今や旅を検討するときに、本当に家を離れる価値があるか?が問われるようになった」
と語っています。
ありうる1つの答えは「娯楽だけではない旅の目的」です。
世界にはさまざまな「特別な目的のために旅をする人たち(○○好き旅人)」がいます。
例えば「バードウォッチング好き」のように、自分の大切なライフワークを実現するための
旅は、他の場所では代替が利かないのでニーズが強いのです。
もう1つの可能性は「教育」でしょう。レジャーやバカンスだけであれば、近場の観光地でも
よいと思ったとしても、学びを通した自己変革のため、あるいは子どもの教育のため
「自国にいては得られない気づきと成長のために動く」というのは、強い動機になりえます。
Stay at Homeの期間に、National Geographic Travelerが「Stay Inspired(インスパイア
され続けよう)」というコンテンツを発信したり、Airbnbが瞑想、料理教室、文化講座
「オンラインでの体験」のプログラムを充実させてきましたが、新型コロナは「旅と学びの
距離を近づけた」と言えるかもしれません。
②クリーン、サステイナビリティ、旅先を選ぶ基準が変わる
旅先を選ぶときには、観光コンテンツの魅力、価格、アクセスなどは重要な要素ですが、
新型コロナの後には別の基準も重要になります。
やはり「クリーン(清潔)」というキーワードは欠かせないでしょう。例えばシンガポール
では、政府観光局が中心になって「SGクリーン」という認証制度が始まりました。
ホテルの場合、室内の衛生状態、温度や消毒の回数、従業員の呼吸器の症状の確認などの
基準が設けられるそうですが、このような制度が各国で導入され、安全と信頼をPRすることが
必須になります。
もう1つは「サステイナビリティ(持続可能性)」です。フランスのメディアUsbek&Ricaの
Pablo Maillé氏は「エコツーリズムやサステイナブルツーリズムが、コロナ危機後の良心的
な選択として再トレンドになる」と指摘します。
もともと、2015年に国連がSDGs(持続可能な開発目標)を発表した頃から、こうした旅への
関心は高まっていましたが、とくにバルセロナ、ヴェネツィア、京都のような人気エリアでは
オーバーツーリズムが課題になっていました。
あまりに多くの外国人観光客が来ることで、住民の生活や、文化財、自然環境に悪影響が
出ているので、規制をしながら「持続可能な観光」を目指すという動きです。
この「オーバーツーリズムへの規制」という視点と、コロナ後に「観光客の密集を避ける」
という対応があいまって「サステイナブルツーリズム」の議論が活発化しそうです。
③デジタル、身体性、旅の楽しみ方が変わる
コロナ後は、旅前や旅中の楽しみ方にも色々な変化が起きそうです。
1つは「デジタル」の融合です。すでにオンライン地図やさまざまなオンライン予約サービ
スが旅には欠かせないものになっていますが、今回のコロナの影響で、「そこに行かなく
てもデジタルで楽しめる」と感じるものが増えています。
例えば、体験アクティビティも「旅前にオンラインレクチャー、旅中はリアルで、旅後は
一緒に参加したみんなとオンラインでつながる」といった形で、デジタルを融合させていく
ことでより付加価値が高まる可能性があります。
そしてデジタル化が進む一方で、リアルの旅における「身体性」のニーズも高まると思います。
「デジタル体験」と「身体性を刺激する体験」を
リモートワークでオンライン会議をされた方は、視覚と聴覚に依存した会話を実感されたと
思います。上記のようなデジタルの融合が進んでも、スマートフォンやパソコンのような通常
のデバイスだと、なかなかそれ以外の感覚を刺激するのが難しいのです。
したがって、実際にリアルな観光地で旅人たちが求めるのは、それ以外の五感も含めた
身体性での楽しみです。
画面上の絶景では伝わらなかった肌にあたる風や水の感覚やにおい、お取り寄せグルメだけ
では想像することしかできなかった、その場の雰囲気とセットで楽しめる地域の味。そして、
対面でコミュニケーションをするときの独特の空気や間。
こういった、ある意味でデジタル体験のコントラストとなるような身体性を刺激する体験は
、観光地の魅力をさらに高めていくはずです。
------------------------------------------------------------------------------
うどんツーリズムは、わざわざ1杯のうどんを食べる為に海を渡って四国まで来るわけです
から、まさに上に指摘されている海外の部分を 【 瀬戸内海を渡って 】 と読み替えて頂けたら
うどん業界に取っても参考になる部分は大きいと思います。
昭和43年に県外人がうどんを足で踏んでいるのを不衛生だとクレームを付けたことでうどん
業界が機械化され、全国に数多いご当地うどんのひとつにすぎなかった 【 さぬきうどん 】 が
大量生産が可能になり 【 日本一のうどん 】 になった訳です。
また製麺機械の開発自体が美味しいうどんの製法を追求することになり、さぬきうどんが
これ程美味しくなり全国に知られるきっかけになりました。
今回のコロナ危機を、将来のさぬきうどんの発展へ繋げるためにも、うどん屋さんの意識改革
が必要となっています。
RNC特選うどん遍路
過去の清水屋 高松成合店 訪問記
8月7日

1月4日

8月16日

7月19日

12月12日

8月21日

10月15日

6月29日

1月16日

10月10日

清水屋 高松成合店
住所: 香川県高松市成合町8 地図
電話 087-886-3212
営業日 日曜定休
営業時間 10:00--14:00