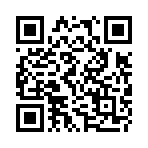2021年10月20日
Posted by {^L^} at
2021年10月20日08:00 Comment(0)
三好うどん

三好うどん
空気がすがすがしいので、昨日に引き続いてちょっと遠出しました。 みよしうどんの前を13時頃通ったら行列が無かったので、急いで坂を下り店内へ。
カウンターが空いてました。\(^^)/








最近しょうゆうどんを食べる機会が多いので、みよしの剛麺を醤油で食べてみましょう。・゚・。・゚・。・♪ ここはお座敷天ぷらが食べられるので、調子に乗ってゲソ天と、レンコン天も頼みました。
ちょうど次の釜の出来立ちが運ばれて来ましたが、見るからにエロいですねっ! 醤油をかけると一段とエロいオーラを放ちます。







すすってみても、剛麺と言うより喉に吸い付くような食感です。 最近大将があちこちへ麺活してるので、ちょっと麺が変わったんですかね。 まあ喉が喜ぶ食感で歓迎です。
小麦の香りもバッチリで、この路線で走っても良いんじゃないでしょうか。 エロくてさぬきうどんらしさも保ってます。
このうどんが200円で、お座敷天ぷら2個食べても400円と言うのもさぬきうどんらしさを感じます。 クリエータの大将も食べ歩きに新しい目標を見いだしたんでしょうかね。
ロケーションと合せて、うどん巡礼のディスティネーションとしては最高ですねっ!
コロナのお時間です
コロナの新規陽性者の急減の理由が色々言われてますが、マスク論、人流論では説明しきれない部分が大きいですね。 職場とかのワクチン接種率が上がって70%とか80%になって、人が集団にな場所の集団免疫が達成したと言う説はかなり有力に思います。
プラスして、元々身体の免疫が高く、ワクチンを打たなくても感染しない人や、山間部でそもそもウイルスに接する機会がない人。 離島もそうですよね。 加えてニュースに出て来るように、コロナワクチン1回目接種 全人口の75%余 と言う感じで、ワクチン接種率の分母は全国民となっているので、乳幼児や幼稚園児を引くと実質80%以上の接種率になっていると考えられなくもないです。
ウイルス自壊論もかなり有望だし、今回毎日新聞が書いたようにウイルスの自然の摂理説も有力に思います。 とにかく過去にも限りなく拡大を続けたウイルス禍は無いわけで、宿主が死ぬとウイルスも生きていけないと言う自然の摂理が働いてるのではないかと言う説です。
まあ昨年の早い段階から言われていたことですが、昨年ではそこまで待てるかいっ! とあまり期待されなかった説ですが、これだけコロナが長期化してくると、その自然の摂理に期待するのもありと思います。
イギリスなんかでは、また感染が増えてますが、確信犯で実際に感染をゆるやかに進めて、集団免疫を目指しているのではないかとも推測されます。おまけに、コロナで重症化や死亡するのは、アーリア人が主だという説もあり、逆に言うとアーリア人以外は騒ぐことは無いと言う考え方もあります。 実際東南アジアではほとんど感染が広がらない訳で、ファクターXと言うよりファクターゼロと言った方が良いのかも知れません。
コロナ新規感染急減の理由は? ウイルスの「生存戦略」という見方も
出典:毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20210919/k00/00m/040/146000c
この夏猛威を振るった新型コロナウイルスの感染「第5波」。大阪府では9月1日をピークに新規感染者が急減している。全国的にも同様の傾向で、政府新型コロナ対策分科会の尾身茂会長は理由を「複合的」と表現した。幅広い専門家に聞くと、夜間の人出抑制、ワクチン効果などを挙げる意見の一方で、ウイルスの「生存戦略」を指摘する見解もある。メッセージは「警戒を緩めるな」だ。
人流の変化が関係?
府内の1日当たり新規感染者数は9月1日に過去最多の3004人を確認。初の3000人台で同日の東京(3168人)に匹敵する数字だった。しかし、1週間後の同8日は2012人、2週間後の同15日には1160人に減った。
「考えられる要素は複数あるが、これは、というのはない」。9月9日に開かれた大阪府新型コロナ対策本部会議で、感染者減少の理由を問われた藤井睦子・健康医療部長はこう説明し、「これまでの波のように、何らかの自粛要請をきっかけに急減していく分かりやすい現状になっていないのは事実だ」と吐露した。
データで関連性がうかがえるのが、いわゆる「人流」の変化だ。筑波大の倉橋節也教授(社会シミュレーション学)によると、東京や大阪では夜間の人出が感染者数と相関関係があるという。
ソフトバンクの子会社「アグープ」のデータを基に分析すると、大阪府に4回目の緊急事態宣言が出た8月2日以降(9月8日まで)の梅田駅の午後9時台の人出は、第4波の感染拡大前(3月1日~4月4日)の同じ時間帯に比べて約30%減少した。SNSの分析では8月以降、カラオケや飲み会、バーベキューの投稿が4分の1程度になったという。倉橋教授は「東京五輪の閉幕(8月8日)後は、コロナによる医療逼迫(ひっぱく)などが多く報じられるようになった。お盆中の長雨もあり行動抑制につながった」と分析する。
大阪大感染症総合教育研究拠点の中野貴志教授(原子核物理学)は「職場や家庭など身近な所まで感染者が出ると、普段会わない人と接触を控えるなど行動変容が起きるのではないか」と推測。「これまでも一定期間で感染は収まっている。ただ、ピークアウト後の感染者の減少速度は第1~4波はほぼ同じだったが、今回は10%以上速い」と指摘し、ワクチン接種が進んで感染しやすい人が減ったことを理由に挙げた。
気温の変化も要因の一つか
患者の治療にも携わる関西福祉大の勝田吉彰教授(渡航医学)は、気候が生活環境に影響を与えたとみる。大阪市の最高気温は8月中旬以降、平年を下回ることが多かった。「冷房中は周囲への気兼ねもあり部屋の窓を開けにくいが、涼しくなれば抵抗感も薄れる。換気の効果があるのでは」と考察。また、百貨店の地下食品売り場でクラスターが相次ぐなど身近なニュースもあり、「一人一人が考えて外出を控える行動につながったのでは。マンネリとされる緊急事態宣言の効果もゼロではなかった」と言う。
これらは「人」に着目した見方だが、昼間の人流が抑え切れていないなど疑問も残る。今回の事態をウイルス側から考えるのが、ワクチン開発に長年取り組んできた大阪大感染症総合教育研究拠点長の松浦善治教授(ウイルス学)だ。
専門家「新たな波は来る」
ウイルスは生きた細胞の中でしか増殖できない。感染した細胞(生物)が死ぬほど病原性が高すぎると、ウイルス自体も効率的に増えられない。そのため、絶えず変異を繰り返して感染力や病原性を変化させ、生き残りを図る。その過程で感染の増減も起きる。
多様なウイルスと格闘してきた松浦教授は「インフルエンザは季節性で新しい変異が少し入りながら冬に流行する周期を繰り返すが、新型コロナは非常に変異しやすい」と説明。「人間界に広がってまだ間もないので、人とウイルスがお互いに探り合いながら落としどころを探しているプロセスなのでは」と推察する。今回の感染急減も収束と拡大を繰り返す局面の一つと考えられるとし「感染が一時的に減少しても新たな波は来る」と警鐘を鳴らす。【松本光樹、高野聡、近藤諭】
RNC特選うどん遍路
過去の手打ち 三好うどん 訪問記: 比地店
11月28日

1月21日

5月10日

3月25日

7月15日

4月29日

過去の手打ち 三好うどん 訪問記: ★旧店
4月29日

手打ち 三好うどん
住所: 香川県三豊市高瀬町比地1583-1 地図
電話 090-1000-7908
営業日 日曜日定休
営業時間 10:00~14:00