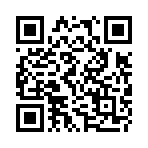2022年08月03日
Posted by {^L^} at
2022年08月03日08:00 Comment(0)
冷やししっぽく@ヨコクラうどん

冷やししっぽく@ヨコクラうどん
暑いですねぇ~ なんと今日の高松は37度だったそうです。(@@) こんな日は激辛のものや、冷たいものが食べたくなりますね。
インディー君を誘って、鬼無の 【 ヨコクラうどん 】 さんの冷やししっぽくうどん行ってみましょう。・゚・。・゚・。・♪




駐車場にクルマを停めて、古い方の店内を通ってお店に入ります。
江戸時代に創業したと言われる香川で一番古いうどん屋さんです。 立派な建物にも老舗の風格が現れてますね。
最近来てないので、ヨコクラうどんさんの 【 冷やししっぽくうどん 】 は食べた事が無いんですが、麺友さんの評判もよく、うどん市場めんくいさんの冷やし野菜うどんより有名になってます。

入り口に置いて有る看板に 【 甘めな気分に 】 と書いて有りますね。 甘党の{^L^}は望むところです。笑
天ぷらも見事なラインナップで目の毒です。 本日限りと書いてあるロングアスパラ天を食べたい衝動をこらえるのに苦労しました。笑 イリコの天ぷらも気になりますねっ!















レジ横のスプーンを取って、ネギと生姜と天かすを入れます。 スプーンは使用済みの箱に入れるようになっていて、ワンウェイです。
店内が暗くて、位置口に近い席に座ると入って来る光でうどんが白飛びしてしまう、スマホには難しい条件です。 ナイトモードになってシャッタースピードが1秒になるので、スマホがぶれないように脇を締めて撮りますが、うどんの持ち上げショットも有りますからね。汗
なかなかビジュアルは良いうどんですが、麺を啜ってみても出汁も旨いですね。 鶏肉から良い出汁が出ているようです。



冷や掛け出汁がベースだと看板に書いてましたが、鶏肉とか野菜から出た旨みが出汁を一層美味しくしている感じですね。
冷たいかけうどんの場合、小麦の香りを引立てない出汁が多いのですが、この出汁はうどんとマッチングがよく一体感があります。
書いて有ったように、ちょい甘めですが、それがまた香川県民には響きますね。 妙な甘さではないので、キリリと引き締まった出汁になっていて気に入りました。
最近覚醒した若大将なかなかやりますね。 スタンンプラリーをひっぱって行く力も流石です。 鬼無方面は連れのうどん屋があまり無いので、バイパスの方の11号線を走ってしまいがちになりますが、こりゃまた鬼無にも来ないといけないですね。汗



コロナのお時間です。
今日もまた東京の陽性者は頭打ちになってますね。 検査できない人が増えている事はともかくAIの予想が一応当っているような形になってます。
このままピークアウトしてくれると良いのですが。。。

昨日の松田政策研究所のオミクロン情報の中で、デルタ株とオミクロンでは感染経路が違うと言う解説をしていましたが、忙しいうどん屋の大将は動画を聞く暇はないでしょうから、{^L^}が要点を書いて置きます。
ようは、オミクロンとその前のデルタとかαは感染経路や感染が成立する方法が違うと言うことです。 その事が、感染予防の方法にも変化を求め、一番大きなポイントは、現行のデルタ&α用ワクチンが効かない事です。
従来のコロナウイルスは、接触や飛沫によって口や鼻から体内に取り込まれ、血管壁のレセプターと呼ばれる受容体とトゲトゲが合致することで、細胞の入り口が開き細胞内へ取り込まれます。 これで感染が成立です。
もちろんこの細胞の量が少なければ発症することなく、自己免疫で駆逐されます。
ところが、オミクロンはこのレセプターを介せず、喉の粘膜に直接結合するように変異した訳です。 ウイルスも生き残るのに必死ですからね。
mRNAワクチンの導入の祭に、毎日TVで報道されたので良く知れてますが、mRNAワクチンはコロナウイルスのトゲトゲの部分の設計図だけ注射し、体内でこのトゲトゲを作り、身体の免疫に攻撃方を覚えさせると言うのがコンセプトです。
その記憶が半年ぐらいで消えるので、追加接種が必要と言うロジックが付いてます。
オミクロンはそもそも、このトゲトゲのレセプターを利用せずに喉の粘膜に侵入するので、mRNAワクチンが効かない訳です。 同じ意味合いで、体内の抗体値が下がっても関係ない訳ですね。
この喉への侵入には、ウイルスが帯電したプラスと、上気道粘膜のマイナスが引き合う制電結合型感染と言う方法が用いられるので、mRNAワクチンは意味をなさない訳です。
それを、5ヶ月が経って抗体値が落ちたから感染が増えているからワクチンの3回目、4回目接種が必要とすり替えている訳ですね。
ご存じのように日本政府は8億回分のワクチン購入契約を結んでいて、その契約はキャンセル不可となっているので、政府は躍起になって4回目の接種を推奨している訳です。 従来のような不活性ワクチンならまだしも、設計図を体内に入れ、どんどんトゲトゲを作らしている訳だから、そのトゲトゲの行き先が気になります。
一部では、それが卵巣に滞留するとも言われてますが、多くのワクチン反対論が出ているので、この事の真偽は分りません。 しかし効くならまだしも、効かないワクチンを打って万が一の副作用があれば取り返しが付きません。
自分で情報を収集整理して自分で判断する必要があります。 下記のようなオミクロン情報は今年の2月にすでにNatureに出ていたのに、それを政府もマスコミも無視している訳ですね。
オミクロン株の構造から急速な感染拡大を説明する
出典:Nature ダイジェスト
https://www.natureasia.com/ja-jp/ndigest/v19/n4/
SARS-CoV-2のオミクロン株は、感染の拡大は非常に速いが、患者の症状は以前の株よりも軽いように見える。ウイルスの構造を調べることで、その理由が見えてきた。
2021年11月に南アフリカ共和国で初めて検出された新型コロナウイルス(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2;SARS-CoV-2)のオミクロン株は、それ以前のどの変異株よりも速く世界中に広まり、ワクチン接種済みの人や過去に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患したことのある人にも易々と感染している。それを可能にした仕組みを明らかにするため、科学者たちは低温(クライオ)電子顕微鏡法などの技術を駆使して、オミクロン株の分子構造を原子レベルに近い分解能で可視化した。
高度に変異したオミクロン株は、体の免疫防御から逃れる能力を獲得し、なおかつ、ヒト細胞を攻撃する能力を維持している。オミクロン株の構造をSARS-CoV-2のオリジナル株や他の変異株と比較する研究から、こうした特徴がオミクロン株の構造のどの部分に由来しているかが見えてきた1。また、この株が引き起こす症状が、既知の変異株に比べて軽いように見える理由も解明されつつある。
デューク大学ヒトワクチン研究所(米国ノースカロライナ州ダラム)の構造生物学者Priyamvada Acharyaは、「オミクロン株の構造は、これまで知られているどの変異株とも大きく異なっています」と言う。
オミクロン株には、研究者が中国の武漢で最初に検出したオリジナルのSARS-CoV-2株には見られない変異が何十個もある。これらの変異の30個以上は、コロナウイルスの表面のスパイクタンパク質(ウイルスが宿主細胞に結合して感染するのを助けるタンパク質)にある。それまでのSARS-CoV-2変異株で、オミクロン株ほど多くの遺伝子変化を蓄積したものはなかった。
オミクロン株のスパイクタンパク質の変異のうちの15個は、このタンパク質の受容体結合ドメイン(RBD)にある。RBDは、ウイルスがヒト細胞に侵入する際に、ヒト細胞表面のACE2受容体に結合する部位だ。ワシントン大学(米国シアトル)の構造生物学者David Veeslerらの研究チームは、この15個の変異と、スパイクタンパク質のN末端ドメインと呼ばれる領域の11個の変異により、オミクロン株が、中和抗体に認識されるウイルスタンパク質領域の構造を完全に作り替えていることを明らかにした2。中和抗体とは、COVIDワクチンの接種やSARS-CoV-2感染を経て体内で作られるようになるタンパク質で、ウイルスを認識して細胞への侵入を阻止する。従って、中和抗体が認識する部位の構造が変化すると、中和抗体の多くはウイルスを認識しにくくなる(2022年2月号「図表で見るCOVIDワクチンの1年」、同3月号「『キラー』免疫細胞はオミクロン株も認識する」参照)。
オミクロン株が、構造をこれだけ変化させているにもかかわらず、まだACE2と強く結合できる理由は大きな謎だ。ブリティッシュ・コロンビア大学(カナダ・バンクーバー)の構造生物学者であるSriram Subramaniamは、「これほど多くの変異があちこちに生じていたら、受容体と結合する能力も低下するのが普通です」と言う。
プラスの効果とマイナスの効果
Subramaniamらは、オミクロン株のRBDの変異の中にはACE2との結合能を低下させるものもあるが、結合を強化するものもあることを示して、この疑問に答えた3。例えば、K417Nという変異は、スパイクタンパク質とACE2との結合を助ける重要な塩橋(タンパク質の中の正に帯電した部分と負に帯電した部分の間の結合)を破壊する。しかし、他の変異の組み合わせが、新たな塩橋と水素結合の形成を促して、ACE2との結合を強化している。その結果、オミクロン株はSARS-CoV-2のオリジナル株よりも強く、デルタ株と同程度の強さでACE2に結合するようになったというわけである。
Veeslerらは、オミクロン株ではRBDとACE2との相互作用が強化されていることも発見した2。「オミクロン株は、変異によって免疫回避能を獲得しつつ、受容体との結合能を強化するという、非常にエレガントな分子的解決策を採用したのです」とVeeslerは言う。
カロリンスカ研究所(スウェーデン・ストックホルム)の構造生物学者であるMartin Hällbergは、これらのグループの研究を賞賛するが、一部の中和抗体がまだオミクロン株を認識できる理由は解決されていないと指摘する。中和抗体がオミクロン株を認識する構造的根拠を解明することができれば、その知識は、将来出現する変異株への対策に役立つだろうと彼は言う。
カロリンスカ研究所(スウェーデン・ストックホルム)の構造生物学者であるMartin Hällbergは、これらのグループの研究を賞賛するが、一部の中和抗体がまだオミクロン株を認識できる理由は解決されていないと指摘する。中和抗体がオミクロン株を認識する構造的根拠を解明することができれば、その知識は、将来出現する変異株への対策に役立つだろうと彼は言う。
オミクロン株には、鼻や喉に感染しやすく肺には感染しにくいという特徴もある。オミクロン株感染に伴う症状が、他の変異株が引き起こす症状に比べて軽い理由は、この特徴が関係しているとみられる。この点についても、構造研究から手掛かりがもたらされている。
多くの研究は、SARS-CoV-2とその変異株が、ヒト細胞のACE2に結合して細胞内に侵入する際に使う2つの経路に注目している。1つは、ウイルスが宿主細胞のTMPRSS2という酵素の助けを借りて細胞と融合し、細胞内に遺伝物質を直接注入する経路。もう1つは、ウイルスがエンドソームと呼ばれる小胞を通って宿主細胞内に入り、その中身を放出する経路で、より時間がかかる(2021年10月号「新型コロナウイルスが細胞に侵入する仕組み」参照)。
いくつかのグループは、オミクロン株が後者のルートを好む証拠を発見した4。例えばVeeslerらは、TMPRSS2経路にはスパイクタンパク質の切断が必要だが、オミクロン株ではデルタ株に比べてこの切断の効率が悪いことを発見した5。研究者らは、オミクロン株が鼻や喉に感染しやすい理由は、TMPRSS2が上気道よりも肺に多く存在していることで説明できるかもしれないとも述べている。
しかし、オミクロン株が後者の侵入経路を好むことに全ての研究者が同意しているわけではない。ハーバード大学医学系大学院(米国マサチューセッツ州ボストン)の構造生物学者Bing Chenは、どちらの説とも少しずつ異なるメカニズムを提案している。彼によれば、オミクロン株感染の症状の軽さはACE2に関連しているという。
ウイルスのRBDがACE2と結合するためには、「ダウン型」の構造から「アップ型」の構造に変化する必要がある。Chenらはプレプリント論文6で、オミクロン株のRBDが、変異の1つによって引き起こされた構造変化のため、アップ型の構造をとるのが難しいことを示す証拠を報告した。その結果、オミクロン株が宿主細胞と融合するためには、他の変異体よりも多くのACE2を必要とする。「一般に肺細胞は上気道細胞に比べてACE2がかなり少なく、オミクロン株が肺細胞に感染しにくい理由は、これにより説明できるかもしれません」とChenは言うが、さらなる研究が必要だとも付け加える。
研究者たちは、オミクロン株の構造に関する知見を、この株に対するより効果的な治療法やワクチンの開発、そして、今後出現するVOC(懸念される変異株)に対するワクチンの開発に役立てたいと考えている。「オミクロン株は、私たちの変異株に対するイメージを覆しました」とVeeslerは言う。
過去のヨコクラうどん 訪問記 :
5月20日

ヨコクラうどん 四国新聞さぬきうどん遍路のページ
住所: 香川県高松市鬼無町鬼無136-1 地図
電話 087-881-4471
営業日 木曜日定休 2024年更新
営業時間 8:00--16:00